今日は良い天気です。気温もどんどん上昇しています。頭にはタオルを巻いて麦藁帽子、ズボンは昨日買ったショートニッカです。動きやすくてよさそうな感じ。
① 砕石の転圧
昨日、家屋西側に砕石を撒いた箇所を自作転圧機にて転圧して行きます。長靴で踏みつけて少し沈む感じがしますのでしっかり転圧しましょう。一定のリズムで転圧をして行きます。5号砕石の方が1回で締まった感じがします。6号砕石の方は敷き厚さが薄いもあってあまり締まった感じがしません。全体を2回転圧しましたがもう一息という感じですが既に腕はパンパンです。
こういう時は他の作業を先にやりましょう。

犬走部。

1、2の間。

2、3の間。

3、4の間。

4、北側三角果樹スペースの間。

北西側雨水桝エリア。

② 型枠の設置
型枠は前に使ったものを再利用しますが、コンクリートと剥離しやすいように油分としてキシラデコールを2度塗りして乾かしておきます。
さて、犬走の部分に木の型枠を設置して行きます。以前打設した土間コンと隣接する部分から設置スタートです。基礎からの仕上がり寸法を確認し、レベル糸に合わせて上部を決めて、基礎側に木杭を打って型枠板をビスで固定します。型枠が撓みそうな所と継ぎ目部分にはちょうど良い寸法で切った木のアジャスターで撓み防止として家屋基礎との隙間に挟んでいきます。
予定箇所が全部設置できたので横から目視すると曲がっているし高さも真っ直ぐではありません。
これは基準であるレベル糸が弛んでいた事と、家屋基礎の一部が膨らんでいた事によります。
再度、型枠の両端に合わせてレベル糸をピーンと張り、修正箇所を確認しビスを外して木杭を打ち直し、高さを合わせて片方をビス止めし、水平器で水平を確認しながら反対もビスで固定しました。2度手間となりましたが、2回目は真っ直ぐに設置できていることを確認できました。

油性を2度塗りました。

型枠を修正して真っ直ぐになりました。

撓みそうなところはアジャスターを挟む。
③ 北側の仕切りレンガ勾配
型枠の角も設置して位置が確定したので、その角から北側の擁壁までの仕切りレンガの勾配を再度確認しました。すると下地の砕石が高いので転圧機で力いっぱい転圧しモルタル厚さ分砕石高さを下げることができました。

角のポイントが決まったので勾配をチェック。

砕石高さを下げるのも大変です。
④ 擁壁、ブロックの洗浄
生コン打設に向けて、仕上げ面に土が付いているとコンクリートの密着が悪くなります。また、ブロックには仕上げ高さがわかるように養生テープを貼るつもりです。
そのため、バケツに水を用意し昨日買った大きなタワシで土をゴシゴシ洗い流しました。洗浄する箇所は、それなりに距離が有りましたのでこれでも結構体力を奪われます。

たわしでゴシゴシ。

ブロックも雨の泥はねで汚れてました。


この辺は土も積んでいたので汚かった。


これならコンクリートもくっ付きます。
⑤ 仕切りレンガ仮置きとレベル調整
仕切りレンガの予定箇所全てにレンガを仮置きしてみます。
家屋側からの水勾配をレベル糸で確認すると道路側のレンガを設置する砕石の高さが高すぎます。一度、ある程度のエリアを鍬を使って砕石を削り、土を数センチ掘って土を撤去し砕石を薄めに撒いて転圧しました。再度レベル糸と道路側のレンガの高さを確認すると10㎜程度ですが糸より下がりました。これを4カ所やりましたがかなり体力が削がれました。

こんあ感じになる。

目地が入ればいい感じに。

⑥ レンガのカット
この時期になると7時半くらいまで明るくて作業をする気ならできますが、体力も限界に近づいています。
仕切りレンガの中で、定尺のまま使うと既存のコンクリートに当たる箇所が3カ所、25−30㎜程度の隙間を埋める箇所が4カ所あるので、ベビーサンダー(ディスクグラインダー)を使って写真のように加工し準備しました。
明日は強い雨が続くようです。晴れ間があればレンガ仕切りを進めたいところです。

それぞれの箇所で寸法が変わります。

モルタル厚分削って。


ブロックの基礎が地面の下で斜めに出っ張ってます。



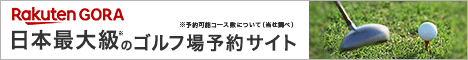




コメント